Vol.31
ヨーグルトの文字
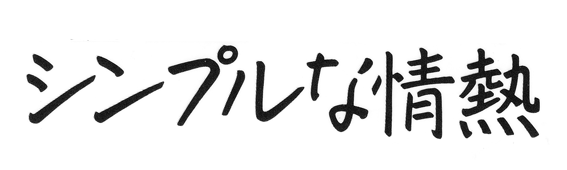
この文字は、白い。
文字の印象が「白」だなんて、妙なことをいう、と思われるかもしれない。
「白」は「無」をイメージさせる色でもあるけれど、この場合、味がしない、という意味では決してない。文字の背景にある白い部分が、線に隔てられることによって際立ち、よりいっそう映えるような感じ。
私はその「白さ」が好きだ。何もないところに文字がかかれるということは、結局、その白さをいかように残すか、ということだともいえる。
文字の白。線と線のあいだに透けてみえる白。
それはヨーグルトの白さに、すこし似ている。乳清、と呼ばれる上澄みの部分に栄養があるのだと、だから残さずにすくって食べなさい、と、子どものころにいわれた。あの、淡泊で、ぽってりとした白さ。仄かに酸っぱい風味もする。
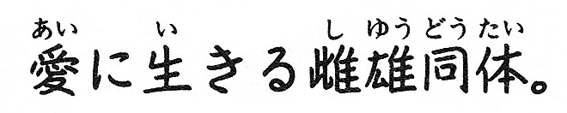
あのころ、とにかく印象的だったのは、この書体の滑らかさだ。生理的で、すべすべしたクリームみたい。
書体に性別があるとしたら、間違いなく〈ナカフリー〉は女性だ。長いあいだそう信じて疑わなかったのだが、この書体は、前出の中村征宏氏が「ふだん妻がかいていた文字を、大きさや中心が揃うようにデッサンし直して」つくったものだという。
あのきわめて男性的な〈ゴナ〉と、〈ナカフリー〉が、同じデザイナーの手によるものだ、というのはにわかに信じがたいけれど、そのエピソードを知った後では、すごく納得のいくことのようにも思える。
というのは、〈ナカフリー〉の「女性らしさ」は、まったく媚びを含んでいないというか、どこか母性的な感じがするからだ。健やかで、シンプルで、やわらかい。
つくづくユニークだなあと思うのは、書体のイメージが、ときに倒錯した状況で――もちろん計算された演出のもとに――言葉と結びつくことだ。そんなとき、文字は、得体の知れない可笑しみをもたらす。
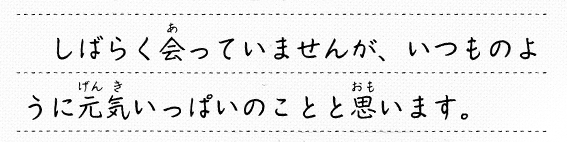
〈ナカフリー〉は、手紙文でよくつかわれる写植書体である。
手紙形式の文章には教科書体も好まれるけれど、〈ナカフリー〉は、教科書体よりかしこまっていなくて、人目につくことを想定していない感じというか、プライベートを直にのぞきみるような気配が漂う。
でも、たとえば、謎の組織から届いた秘密文書とか、身に覚えのない果たし状(もらったことはないけど)とかには、この書体は到底似合わない。
本を読んでいて、この文字でかかれた「手紙」が出てくると、私は、ああ、よく知っているひとからの手紙だ、と思う。名前をみなくてもわかる文字。
どうしてだろう。
実際のところ、自分の身近に、これと似た文字をかくひとはいないのに。それなのに、どういうわけか、私はこの文字に対して自然と好意をもっていたし、一緒に朝ごはんを食べる相手みたいな親しさを抱く。
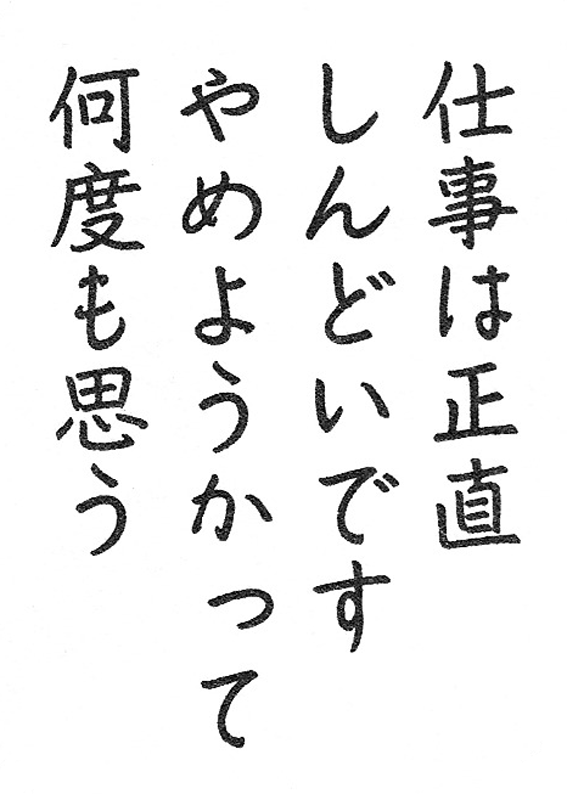
「働きマン」で〈ナカフリー〉がつかわれているシーンも私はすごく好きだ。
初めて読んだとき、この台詞は手紙だ、と思った。どこにも届くはずのない、出されなかった手紙。
そう感じたとき、自分とは別の世界に生きているはずだった登場人物たちは、すでに親しい、近しい存在になっていた。
文字の印象が、限定されたなつかしさを呼び覚ますからかもしれない。
そのひとの文字を知っている、と思えることほど、シンプルに心の距離をはかる基準もないと思う。
「あなたがかいた文字をみれば、私はすぐにわかります」
そんなことを普段わざわざひとに伝えたことはないけれど、口に出してみると、まるで恋心をうちあけるみたいで恥ずかしい。
他人の筆跡を思いだすだけでそうなのだから、好きなひとの文字を「まねする」のは、究極の愛情表現だよなあ。
と、思うのですが、どうでしょう?
