Vol.34
サンドウィッチの文字
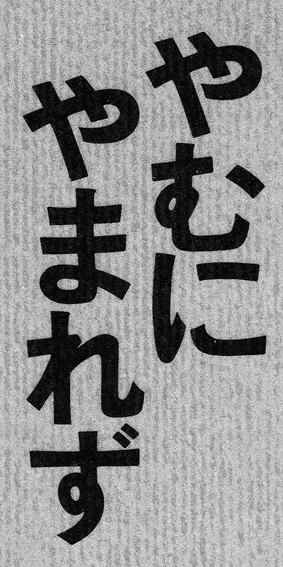
ああ、こまった。
いったいなにがこまるのかって、この書体についてかこうとするとき、〈かな民友ゴシック〉の名前だけを挙げるのはひどくきまりが悪いからだ。
私は今まで〈かな民友ゴシック〉について写研の写植書体だという程度の知識しか持ち合わせていなかったのだが、もともとは民友社という活版製造所の活字書体を写研が写植化したものだそうだ。ちなみにモリサワにも同じ民友社の名前を冠した写植書体がある。
しかし現在、巷に流通しているこれとよく似た文字は〈ヒラギノ角ゴオールド〉という名前のデジタルフォントで、それは民友社とはまた別の、藤田活版製造所の金属活字を見本に字游工房が制作した〈游築初号ゴシックかな〉と、以前からあった〈ヒラギノ角ゴシック〉の漢字を組み合わせて、大日本スクリーン製造からリリースされた新しい書体だという(ああ、こまった。なんのこっちゃである)。
こんなややこしいことになったのも、字形というものの宿命だなあと思うのだが、民友社、また藤田活版製造所のいずれも、明治時代に日本の活版印刷技術を牽引した東京築地活版製造所の活字母型を継承しているためらしい。
このとぼけた味わいをもつゴシック体が、時空を超えて同質性を保っている、という事実は、日本の活字書体のデザインがいかに極められていたかということの証明にも思えてぐっとくる。

勿論、読者にとっては文字の血統や素性を知る必要などないし、目の前で組まれたものがすべてだ、とも思う。
だから正直に告白すれば、私は、この書体に対して、まるでサンドウィッチマンのようなイメージをもっていた。目立つ図体のわりに肩身がせまそうというか、一歩引いている、というか。
活字だったころの名残りというべきか、文字の全体に圧がかかったような密着感のせいかもしれない。
その印象はまさに、いまにも具がこぼれおちる寸前のサンドウィッチを連想させる。それも上品につまむようなものではなく、質素だけれど、きちんとおいしいものを豪快にはさんだ、かたいパンのサンドイッチ。日々の糧を得るために働く労働者の手で、急いでほおばりたくなる。
関川夏央の『やむにやまれず』を読んだとき、この感じにはどこかで見覚えがある、と思ったら『ぼのぼの』(いがらしみきお)だった。
ふきだしのセリフやモノローグはすべて作者の手書きだが、タイトルにつかわれている見出しの文字が〈民友かなゴシック〉である。
「こまるのはそのうちなのに もうこまってる」と言うぼのぼのには、親近感を抱かずにいられない。
「生き物は生きてる限り絶対こまるんだよ。こまらない生き方なんか絶対ないんだよ。そしてこまるのは絶対に終わるんだ。どうだ、少しは安心してこまれるようになったか」というスナドリネコさんの言葉も大好き。
ふつうこまっているときは、こまった状態そのものではなく、そうなった原因や結果の方に気をとられがちだけれど、この文字でかかれたタイトルをみていると、こまった気分というのは、確かにこういうかたちをしてるよなと思う。
この書体をえらんだひとは、なんでそのことを知っているんだろうと思う。

リチャード・ブローティガンの『ホークライン家の怪物』は、本文や発行年をみると活字の時代につくられた本なので、これが〈かな民友ゴシック〉のルーツといえるのかもしれない。
物語が始まっても、怪物はなかなか姿を現さない。
でも、私は、その怪物には名前がないことを知っている。目立つ図体のわりに肩身がせまく、世間からは一歩引いて、やむにやまれず身をやつしていることを知っている。言葉では把握できない感情を抱えて。
私はたぶん、怪物の正体を知りたいのではなく、与えられた印象を確かめたくて本を読むのだ。想像が当たっているかどうかは、この際あまり重要じゃない。
そういうのは悪くないな、と思う。世のなかにはきっと、どこかに同質のものが存在して、それは誰かとわけあえるものにちがいないと、一瞬でも、そう信じられることは悪くない。
私はそのことを文字の力に教えられた。
おかげで、大人になった今、「少しは安心してこまれるようになった」と思っている。
