Vol.35
魚の文字
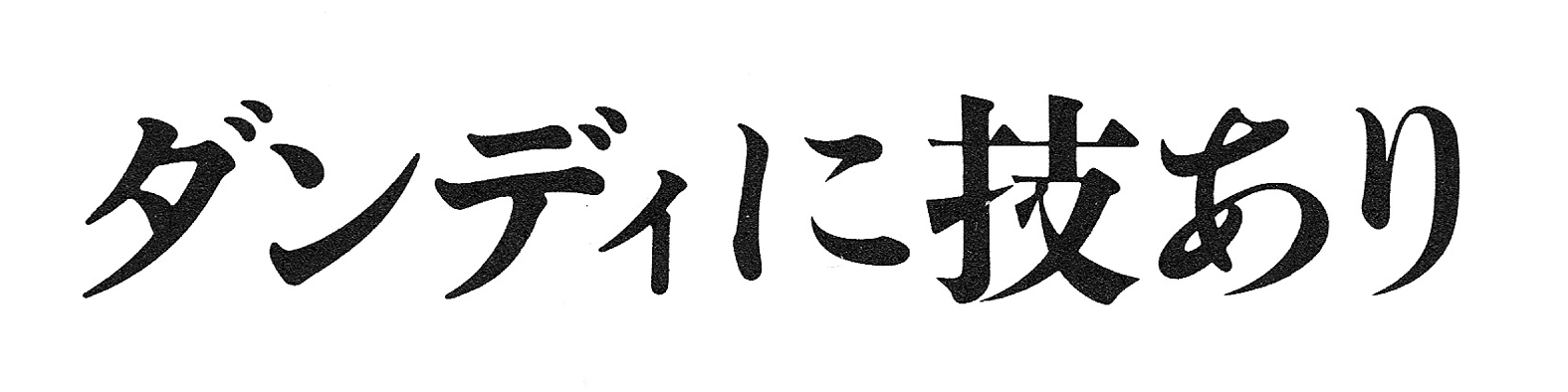
パソコンや携帯電話の画面の明るさとはまったくちがう。
ガラスの文字盤は、身体を通り抜けてしまいそうに深くやわらかい光を放っていて、それをみていたら、私は蛍を思いだした。
不思議だなあ。この光が、文字になるなんて。
先月、大阪で、動く写真植字機をみせていただいた。そんな日がくるとは思っていなかった。
子供のころ、印刷物の文字がどうやってできているのかは大きな謎だった。外国の映画にでてくるようなタイプライターはイメージしやすかったが、キーボードを打つことと、それが文字になることとの間には、どうしても理解できない空白の溝があった(文字化け、なんて言葉は当時、存在していなかった)。
そんなある日、父がMacコンピュータを買ってきた。中学に入って間もないころだ。
薄暗いモニター画面に映しだされた文字を印刷してみると、画面上ではがたがたにみえていたものが、びっくりするほど滑らかになって、自分がかいた文章でも、ちょっと立派にみえることがうれしかった。
文字の印象の違いが「フォント」と呼ばれるもので、それぞれに名前があることも、パソコンのつかいかたを教わってはじめて知った。本をつくることは、きっとこの延長線上にある。そう確信した。
しかし、どんなに「フォント」を探しても、いつも本や雑誌でみている文字は見当たらない。これはいったいどういうわけなのだろう。
そのとき、私が苦しまぎれに考えたことは、父のパソコンと、本をつくるためのパソコンは、きっと階級が違うのだろう、ということだった。高名な音楽家が庶民には手の届かないヴァイオリンをもっているみたいに、そしてその音を聴きたいためにコンサートへ足を運ぶ観客がいるように、文字にもきっと家庭用とプロ用があるのだろう、と。そんなふうに思ってしまうくらい、同じ印刷された文字でも、その印象は決定的に違っていた。
空白が埋まったのではない。
いつの間にか気づかないふりをしていただけだ。
黄緑色に浮かびあがった文字をみながら、そんなことを思った。
「単純な機械なんです」
手動の写真植字機が現役だったのはずいぶん昔のことなのに、すべて体にしみこんでいるという手つきで、すいすいとレバーを操りながら、職人の方が笑って言う。
「でも、ものすごく、うまくできている機械です。こんなんよう考えたなあと思います」
業務用のミシンを巨大にしたような、見映えのしない無骨な機械なのに、ライトがつき、文字盤が照らされたとたん俄に、潜水艦のコックピットさながらの風情が漂う。
大きな印画紙を暗箱にセットし、歯車を調節し、レンズをあわせる。ガシャン、ガシャン、という心地いい確実な音で、文字盤から選んだ文字を印画紙に焼きつけていく。
何の文字を打っているのかはまわりからみえないのに、つい無言になって、手の動きに見入ってしまう。シャッターを切る音だけが響く静寂のなかで、そこには空白がないようにみえた。
学生時代、古本漁りに精をだしていたころ、たまたま見つけた『ダンディに技あり』という本で、「写植印字(カバー・扉・帯)前田成明」というクレジットをみた。そのひとの名前は、「ブックデザイン 日下潤一」と「イラストレーション 大橋歩」のあいだに堂々と並んでいた。
シャショク?
私は首をかしげ、改めて、表紙の文字をまじまじとみた。
「印字」の意味は想像がついたが、「写植」の方は、聞いたことのない言葉だった。もしかして、今までみていたのもずっと、パソコンのフォントじゃなかったのか。
それは私にとって、長年の前提を大きく覆す新事実だったけれど、ああ、やっぱり、というか、自分が思ったほどは衝撃をうけなかった。
そのときにみた文字が、〈秀英初号明朝〉(写研の秀英明朝/SHM)であったことも、心の動きに影響していたかもしれない。
いかにもプロ仕様の、しなやかで、きらめくような文字の印象から、文字を「植える」ひとというより、活きのいい魚をつかまえてきたひとみたいに思えたのだ。
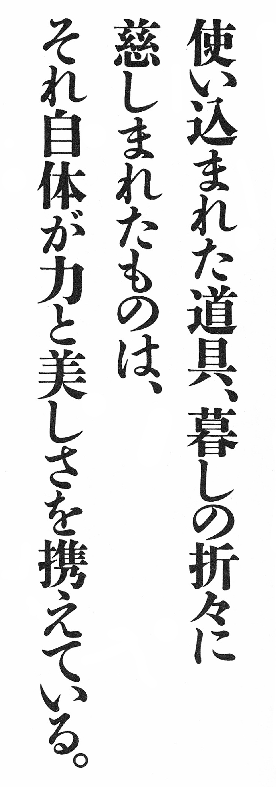
〈秀英初号明朝〉は、長い伝統のある秀英体のなかでも、明治末期、なんと今から100年も前に誕生した「秀英体初号活字」がもとになっている。古いから模範的で型にはまっていると思うのは早計で、その線やかたちはまさに自由闊達。筆の勢いにのって勢いよく跳ねたり、翻したり、そうかと思えば、海の底でじっとしているような目立たない字もあるのがおもしろい。
それが写植でもつかわれるようになったのは1981年のことだ。
デザイン書体のブームで写真植字が飛躍的に普及し、その影響で本物の「活字」が第一線から姿を消しつつあったころ、この書体に強い愛着を持っていたデザイナーの杉浦康平が熱望したことによって写植化が実現したという。
今は完全にDTPに取って代わられている写真植字が、かつては革新的な技術で活版印刷を脅かし、その衰退を早めた存在であったことは皮肉だけれど、デザイナーのプロ意識というより人間の業を感じさせるこのエピソードには心打たれる。
だって、日本語の文化を守るためとか、他人のデザインと差をつけるためとか、そういう理由では納得がいかない。ほんとうは、その書体で組まれたところを自分がみたい、という、きわめて純粋で、自己中心的な感情だったはずだ、と、私は思っている。
「この書体でなければだめだ」と思うことの、人間らしさ。説明のつかなさ。
それに第一、杉浦康平が優れた文字の使い手でなかったら、印刷会社や書体メーカーを動かすことはできなかった。
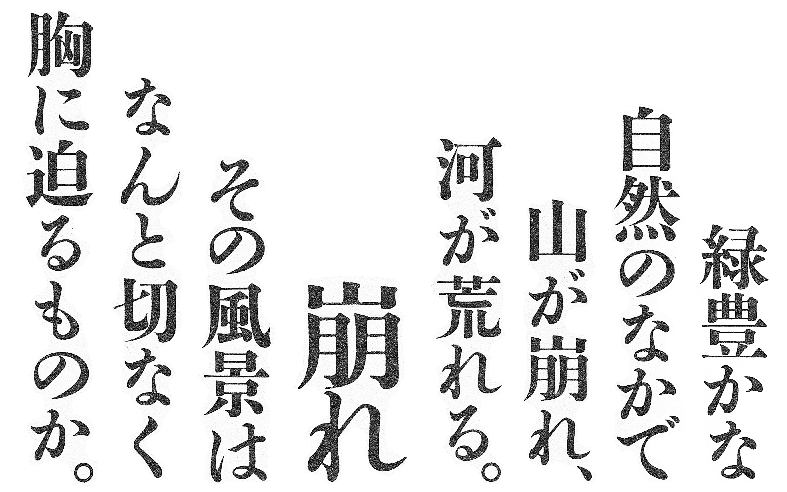
そのころ、文字にこだわりをもつデザイナーは、自分の好みに文字を組んでもらえる腕のいい職人を直接指名することがめずらしくなかったそうだ。前田成明さんという方も、写植の時代に多くの名デザイナーを支え、活躍されたオペレーターのひとりである。
〈秀英初号明朝〉は、デザイナーの根強い支持を受けて数年前にデジタルフォント化され、デザイナー自身がパソコンでつかえる書体になった。もちろんタダではないとはいえ、趣味の延長でこの書体をつかいたいと思えば誰にでも手に入るのだから良い世の中になったものだが、見方を変えれば、家庭用とプロ用の区別が次第になくなりつつあるともいえる。
その変化が何をもたらすのか、私にはわからない。
でも、個人でつかうという選択肢が現実的になって、はじめてはっきりとわかったことがある。
私は書体を「モノ」として所有したいわけではないということ。
この文字でかかれた言葉に感じる、神秘性や、敬意や、畏れの背後にある物語を大切にしたい。
美しい文字を生かすには、それに見合う強い心が求められるのだ。
