Vol.36
こんぺいとうの文字

最近、テレビをつけたら『ふしぎの海のナディア』のデジタルリマスター版再放送をやっていた。夕方で、家のなかには他に誰もいなくて、台所からごはんの炊ける匂いがしていた。
そうだ、子供のころ、ナディアになりたくて、生まれて初めて近所の美容室で髪を切ったら、ただのオカッパ頭にされて愕然としたっけ。そんな、あまり思いだしたくもないことをぼんやり思いだしていたら、エンドロールの字幕スーパーにはっとした。思わず目で追ったけれど、文字は絵の雲や風と一緒にどんどん流れていってしまった。
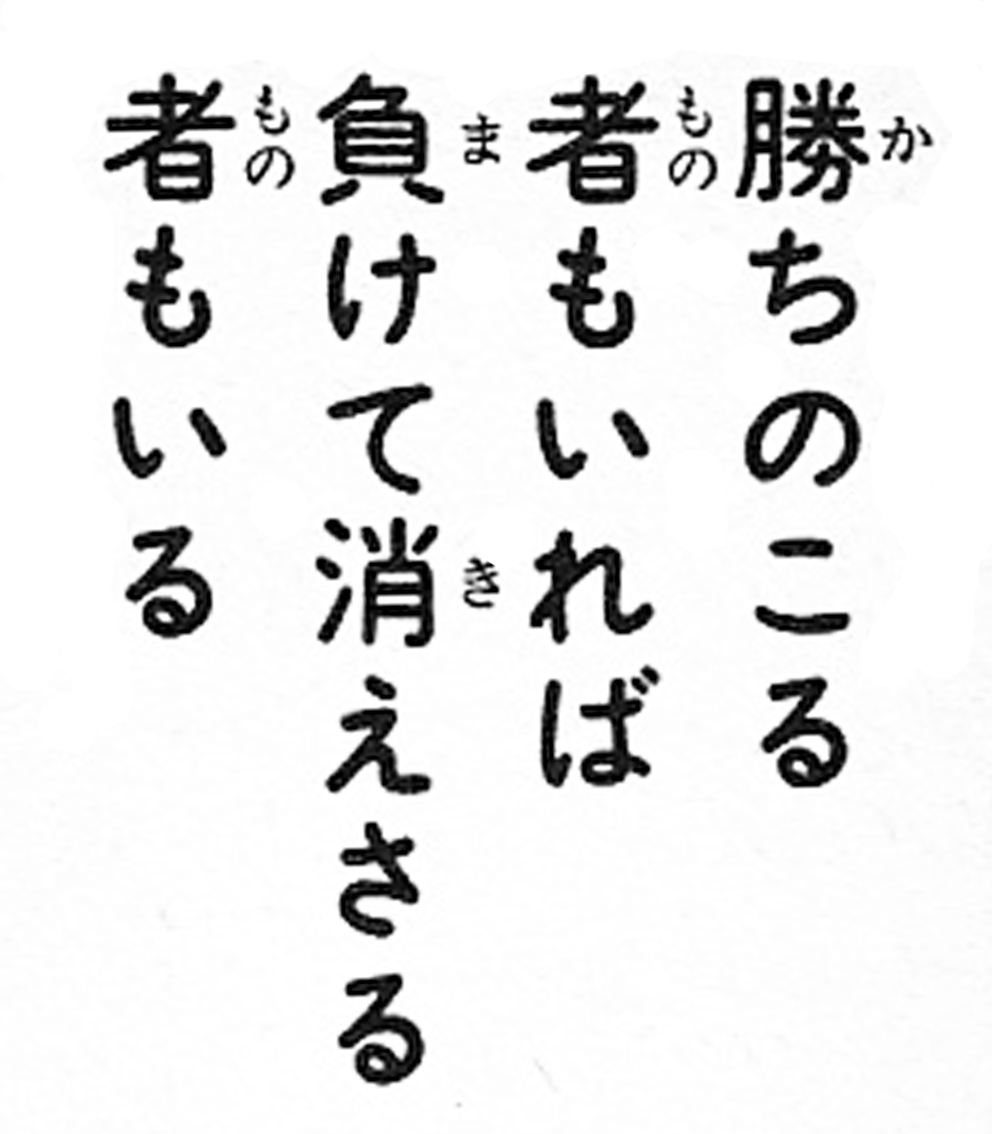
〈石井太丸ゴシック〉は、私が毎週金曜日の夜を心待ちにしていた当時、テレビ番組のテロップでよくつかわれていた書体だ。
テレビの画面でみたのと、紙の本でみたのと、どちらが先だったのかは思いだせない。そのころすでに特別な感情を抱いていたわけでもない。
でも大人になって、この書体を改めてみると、小さな宝物を贈られたみたいに、どきっとするのはどうしてなのだろう。
「時間」というのは不思議なものだなと思う。ありふれた、ふつうのものを、美しくする。
一般的には「レトロ」と表現するのかもしれない。
レトロ。
その言葉の使われ方にはおそろしく違和感があるのに、どうしても感傷がまじってしまう。
そのせいか、私が出会ったなかで、この書体が好きですというひとはいつも、ちょっと照れくさそうな、不本意のような顔をする。かつて純粋な部活少年だったことを白状するみたいに。

いわゆる「丸ゴシック」と呼ばれる、角が丸い、やさしい雰囲気をもったゴシック体なら、デジタルフォントでも選べないほどたくさん出ているけれど、1958年生まれの写植書体〈石井太丸ゴシック〉の個性は今でも唯一無二だと思う。
意識して輪郭を丸くしたというより、自然に角がとれたような丸み。「摩耗」したような角、とかくのは、いくら読者の勝手な印象とはいえ、それは言い過ぎだろうか。
ひとつひとつの文字をみても主張があるようには思われないのに、くっついてかたまりになったとたん、他のどれにも似ていない印象になる。
どういうことかというと、この文字でかかれた言葉は、かすかに甘い、半透明の膜でコーティングされているみたいに感じるのだ。淡い虹のように、不幸ではないけれどかなしい。ちょっと儚い甘さ。
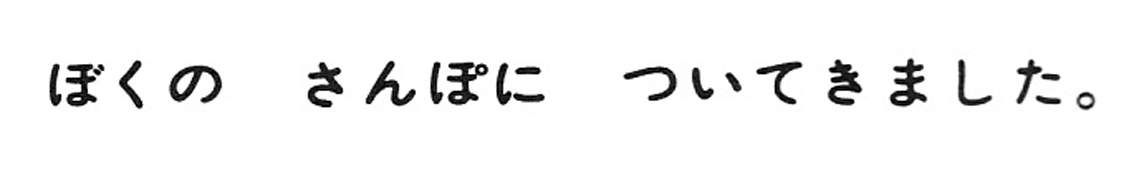
そのイメージと直接関係があるのかはわからないけれど、この書体でかかれていたことを今でも憶えているのは、エッツの『もりのなか』という絵本である。
森へでかけた少年が、散歩の途中でさまざまな動物と出会い、ライオンや、象や、くまを次々となかまにしていく。
いかにも絵本的な繰り返し構造なのだが、ページの先にあらわれる同じ構図と、たんたんとした文章のリズムとが相まって、なんともいえず安心で、豊かな気持ちになる。
一度にたくさんは読みづらく感じるところもいい。
この絵本の最後は、動物たちとかくれんぼうをしているときに父親が迎えに来て、家に帰らなければならなくなった少年の、こんな言葉で終わる。
「みんな、まっててね。またこんど、さんぽにきたとき、さがすからね!」
読み返して初めて、気がついた。
あのころ、私の目には、この一行が、終わりの始まりを告げるエンドロールのようにみえていた。
