Vol.32
蝋燭の文字
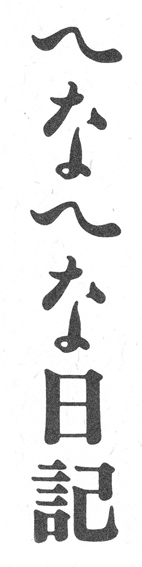
タイトルを聞くからにいかにも率直で脱力したエッセイ集である。
薄墨紙を思わせるグレーの表紙。その題字につかわれていた朱色の文字に、目が釘づけになった。
この本のことはなぜかいまでも覚えているのだが、改めて考えてみれば、かなの部分は「へ」と「な」の二つしかない、ということに気づいて愕然としてしまう。
その存在感は、きっと、不可思議な歪みのせいだ。
一見不揃いのようで、みる者を惑わせる微妙なずれ。そのくせじっと眺めていると、哀しげな表情から温もりが伝わってきて心が安らぐ。
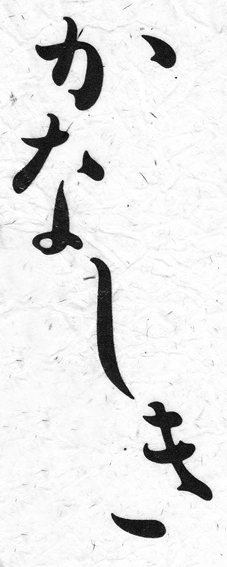
このあやしくておもしろいかな書体は〈良寛〉という名前で、ほんとうに、あの良寛の筆跡からつくられたものだという。
幼少のころから和歌に親しみ、優れた詩人であった禅僧の良寛だが、書家としても有名で、古い名筆と呼ばれる書が残っている。
私にとって、良寛は、手毬をついて子どもたちと遊んでいる江戸時代のお坊さん、いわゆる「良寛さん」のイメージだ。いばったことが大嫌いで、子どもを愛し、「高名な人物からの書の依頼は断っても、子どもたちから凧に文字をかいてほしいと頼まれたときには喜んでかいた」という微笑ましいエピソードも、庶民派の良寛らしい。
この私が良寛の書について語るのは恐れ多いことのように思えるけれど(何しろ私が良寛の字を知ったのは本物より写植書体の〈良寛〉の方が先なのだ)、その筆がいかに型破りであったかは誰にでも一目瞭然だ。
いまにも力尽きて、消え入りそうな、寂寥感の漂う細い線。お世辞にも達筆とはいいがたい。
子どものころ、火をみるのが好きだった。
「オール電化」などという言葉がまだめずらしかった時代ではあったにせよ、私は家事手伝いをろくにしない子どもだったので、火は身近なものというより、興味深い観察対象に近かった。バースデーケーキに立てられた蝋燭も、アラジンストーヴの青白い炎も、クリスマスのキャンドルも。
とくにおもしろいと思ったのは、自分の身のまわりにある目に見えない空気は、意外なほど活発に動いている、ということだった。じっと息をつめているつもりでも、隣の部屋のドアや、ひとの気配で、火のかたちは脈をうつようにゆらめき、重心がどこにあるのか判然としない。
何とか焦点をあわせようとしているうちに、なぜか自分の身体が妙に生々しく感じられたものだ。

写植書体の〈良寛〉が世に出たのは1984年。良寛の筆跡から印刷用書体の文字板をつくるという大それた試みが実現した理由について、設計者の味岡伸太郎氏は、「自分がタイポグラフィの素人であったことだ」と、述べている。
多くのひとの目にふれる書体をつくりたい、とか、文字は万能でなければならない、とか、タブーや要求が一切ない場所にいたからできたことだ、と。
良寛というひとも、本来の書家ではなかったからこそ、もしかして同じようなことを考えていたのではないか。「書道」という大きな流れではなく、目の前の小さいものを照らすようにして、こんな文字をかいたのではないか。
でもそれは、どんなに孤独で、情熱と精神力を要することだったろう。
この書体に宿った面影は、いまも私を惹きつけてやまない。
世の不均衡に耐えながら、焦がれるように、何かを祈っている。そのような文字にみえる。
