Vol.37
滴る文字
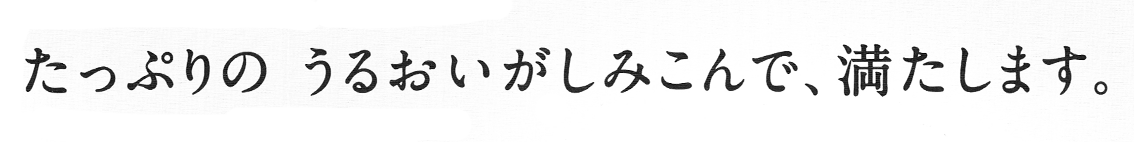
季節の変わり目になると、化粧品の広告にどうしても目がいってしまう。
私は昔から肌が弱いので、実際に使える化粧品は限られていたりするのだが、ファンデーションは新しければ新しいものほどいいとか、新開発の浸透技術だとか書かれると(それでなくても文字に惑わされやすい性質なので)、気もそぞろに新製品を眺める。
すると、時々、化粧品のイメージ写真で、いかにも高級そうな美容液やクリームのびんが、うっすらと汗をかいていることがある。容器の表面できらきらと光を散らす、ふっくらまるい水の粒。
もちろんそれは撮影上の演出だ。誰がみてもわかる。
中身の効果のほどは、写真では確かめようがないけれど、無機質なパッケージを単純に並べて撮っただけのものよりも、何だか良さそうにみえる。水をはじく若葉のような、みずみずしい肌を連想させる。
文字の世界でも似たような演出が行われていることは、でもあまり知られていない。
どんなに心地いい言葉でも、あるいはありふれた言葉でも、選ばれる書体によって、今朝とれたての野菜と、三日前から冷蔵庫に入っていた野菜くらいの違いがある。
その、いわば「朝摘み感」ともいうべきみずみずしさを、私がもっとも感じる書体が〈A1明朝〉である。

〈A1明朝〉はモリサワの伝統的な明朝体のひとつで、かつては〈太明朝体A1〉という名前で愛された写植書体だった。
創業間もない1960年頃、写真植字機の技術では業界をリードするものの、書体の数では写研に水をあけられていたモリサワが「初めて独自開発した太明朝体」であるという。
その優雅でやわらかな表情に、写研の名書体〈石井中明朝体 (MM-OKL)〉の面影があると言うひともいるけれど、私はそうは思わない。〈石井中明朝〉が透明なゼリーだとするなら、〈A1明朝〉はさらに水分量が多くて、溶液に近いような印象がある。
実際の書体見本の解説によれば、「デジタル書体化にあたって、写植特有の墨だまりを再現」したということだが、この「墨だまり」という言葉、辞書をひいても載っていない。書道独特の用語で、ひいては印刷の不安定な滲みや「ボケ味」の意味でもつかわれる場合があるようだ。
この文字でかかれた言葉の、高いところからピチョンと落ちてきたしずくのような感じは、この「墨だまり」と呼ばれる部分から生まれているのだろうか。
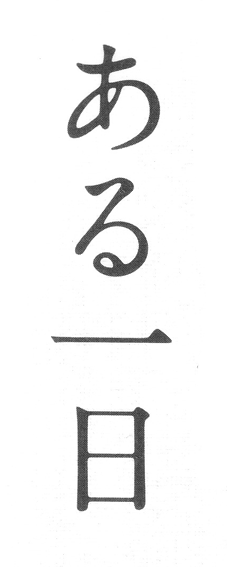
世の中が〈石井明朝〉一辺倒だったころ、ふっと何気なく(でも間違いなく確信犯で)つかわれている〈A1明朝〉は、とても印象的だった。違和感とも呼べないほどの差異なのに、そこだけふしぎな浮遊感があった。
そんなイメージのせいか、〈A1明朝〉で読むなら、(私の勝手な好みだけれど)スタッカートのような短い言葉がいちばん好き。
しずくとしずくが、くっつきそうで、絶対にくっついてしまわない程度の、絶妙な距離を保っているときの緊張感が好き。
いつからそんなふうに感じるようになったのだ、と聞かれても答えられないのだが、自分で発見したというより、誰かの記憶を映像みたいにみているような気がする。
それにしても、近頃は本当にこの書体をよくみかける。
霧吹きでぱっぱと水をかけるような気軽さで、たっぷりと潤った言葉が溢れていて、文字の世界もさながら美白ブームのよう。
ところが最近、小説でもたまにみかけるのだが、この書体でびっしり組まれた長い文章を読んでいると、水気の多いサラダを食べているみたいで、ふっと「読む気が失せる」ことがある。本を読みたいのに。好きな作家なのに。
そんなのはあんただけだ、変なやつだなあと言われても仕方ないけれど(笑われるよりむしろ気の毒なやつだと同情されるかもしれない)、でも、やっぱり、錯覚ではないと思う。
「活字中毒」という言葉が昔からあるくらいなんだもの。私と似たようなことを考えているひとが、絶対にいないとも限らないので、思いきって書いてみた。
味に口うるさい常連客を気どっている私のような人間は、まだいい。
「読む気が失せた」理由など、わざわざ考えようとしない一見の読者が大多数である。そのことのほうがこわいと私は思う。
