Vol.38
ミントの文字
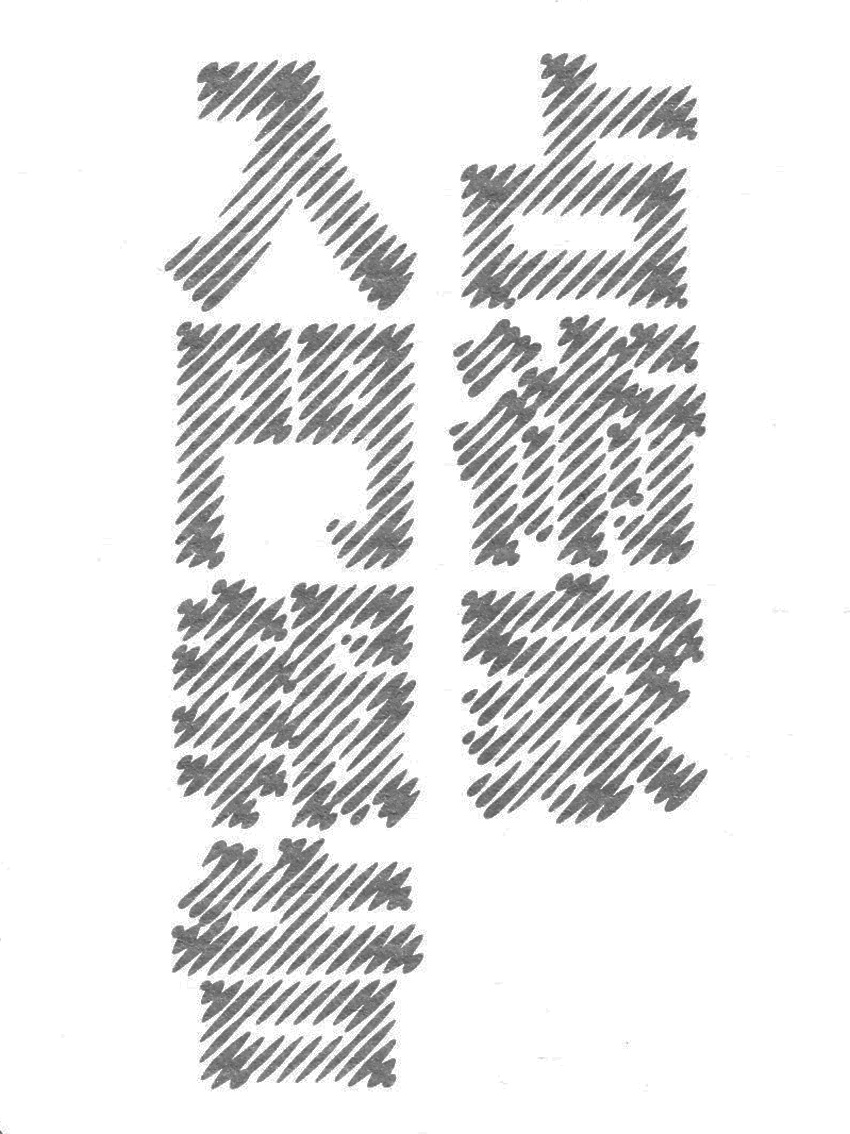
粘着質の文字に弱い。
粘着質、というのは、べたっと目の裏にはりつくような字。起伏が大きい字。圧が強く感じられる字。
そういう文字を見ると、つい引き寄せられてしまう。ずっとそう自覚していたのだが、でも実は、その条件にまったく当てはまらない例外がある。〈ボカッシイ〉だ。
〈ボカッシイ〉もやはり現在のDTPでは公開されていないけれど、80年代から90年代にかけてよくつかわれていた写研の写植書体である。前出の〈スーボ〉のように、ユニークで完成度の高いディスプレイ書体がすでに普及していた当時でも、その登場(第七回石井賞)から〈ボカッシイ〉がとにかく異色な存在だったのは間違いない。
なにしろその字形!
およそアウトラインというものがない。
細部がよく見えないくせに、目にするたびに、初めて見るものを見ているような気もする。
前代未聞、という言葉はあまり好きじゃないけれど、三十年経った今もなお「代用書体」さえ出てこない、という事実が、何よりそのことを証明している。
文字を光らせたり陰影をつけたり、ぼかしたりすることは、いまや書体ではなくてもグラフィックソフトをつかえば簡単にできるのかもしれない。しかしテクノロジーを駆使して加工された文字は、よくも悪くもクリアで雑味がなく、合成香料的な印象があるのに対して、〈ボカッシイ〉の方は、私にとって、香りの強いハーブみたいだ。そのなんともいえない微妙なえぐみは、虫がよりつかない成分を自らだしているとしか思えない。
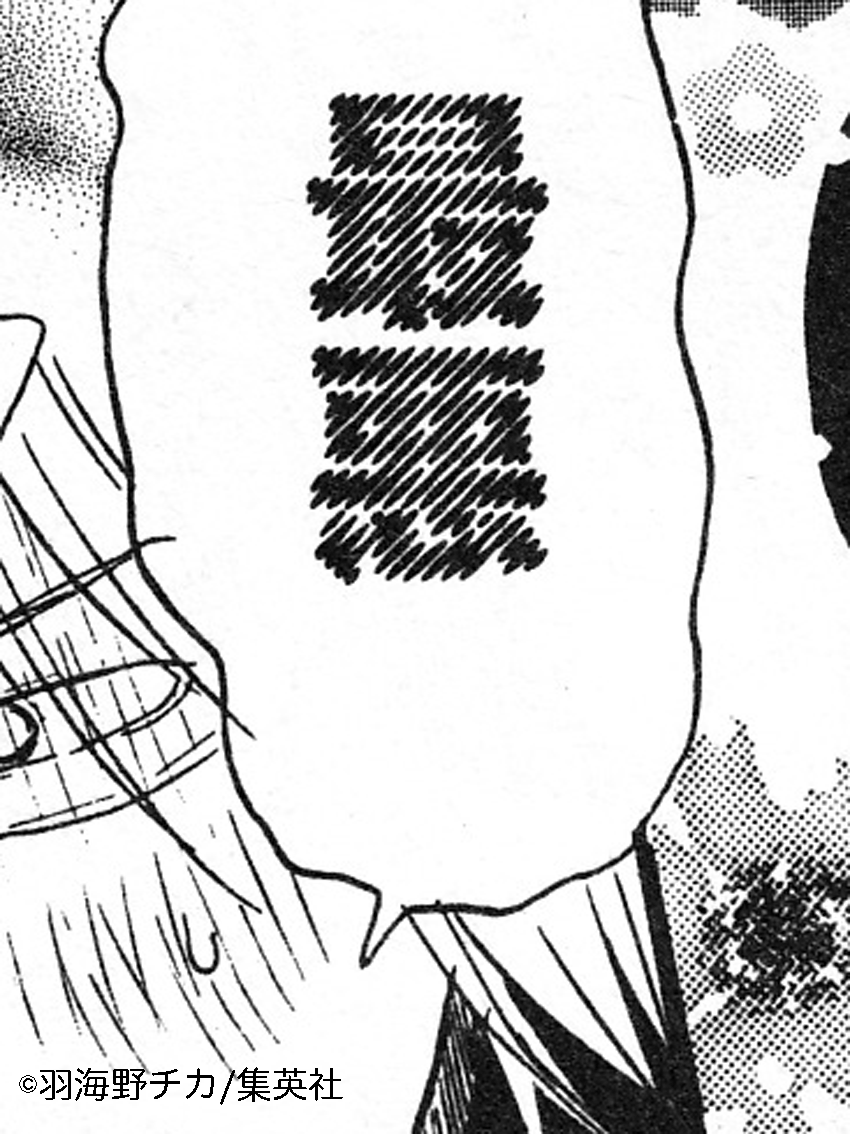
〈ボカッシイ〉の設計者は、後にあの艶書体を制作する今田欣一氏。
伝統的な江戸切子のカットガラスからデザインの着想を得たのだ、ということをどこかで読んだけれど、なるほど、冷たいガラスのように温度の低い文字である。視覚的なインパクトは刺激が強いのに、鎮静作用もあわせもっている、という感じ。
この書体でかかれた言葉には、揮発性のあるメントールみたいに、読後がスース―する清涼感があると思う。
言葉の体温が急激に下がることによって、「興醒め」や「しらける気持ち」、いわゆる現代語で言うところの「引く」という心の距離感が表現されているのはおもしろい。
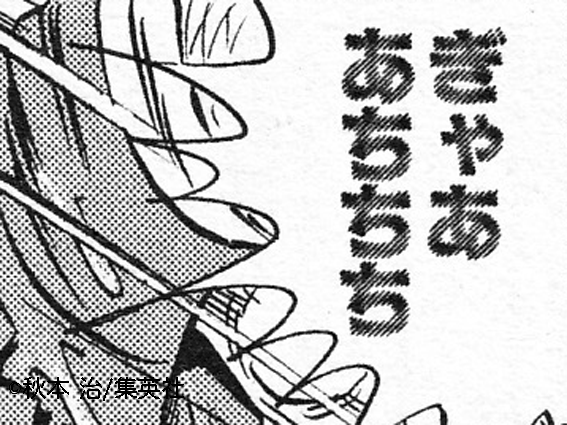
でもたとえば『こち亀』の両さんが熱湯をかぶってしまった場合。
矛盾するようだが、この場合に書体がふさわしくないかというと、そうは思わない。
その言葉が持つ本来の意味と、書体のイメージの大きな温度差によって、熱湯が沸点に達していることや、脳で温度を感じる前に身体が反応しているということが、実際に皮膚で感じていなくても明快に伝わってくる。肌のうえで気化熱が奪われるように、言葉の表面でも同じ現象が起きているのだ。
勿論、この何気ない小さなシーンについて、担当編集者がどれだけ吟味を重ねたのかはわからない。
しかし当時の連載を見ると、ひとコマごと、セリフごとに全部書体を変えていたりして、わずかなしぐさや声音で人間を演じ分ける落語家さながら書体をつかい倒す慧眼には感服する。そして実に500万人もの人々が、そういうものを毎週読んでいて何も不思議に思わなかった、という事実にも。
こんな書体があるなんて気づかなかった、というひとこそ、実は何度も味わっているかもしれない。
無意識のうちに出会ったもの、目にしていたものが、記憶のなかで複雑な屈折を生み、ひとつとして同じものはない表情をプリズムのようにうつしだす。
ほんとうはそんな文字にいちばん弱いのである。
